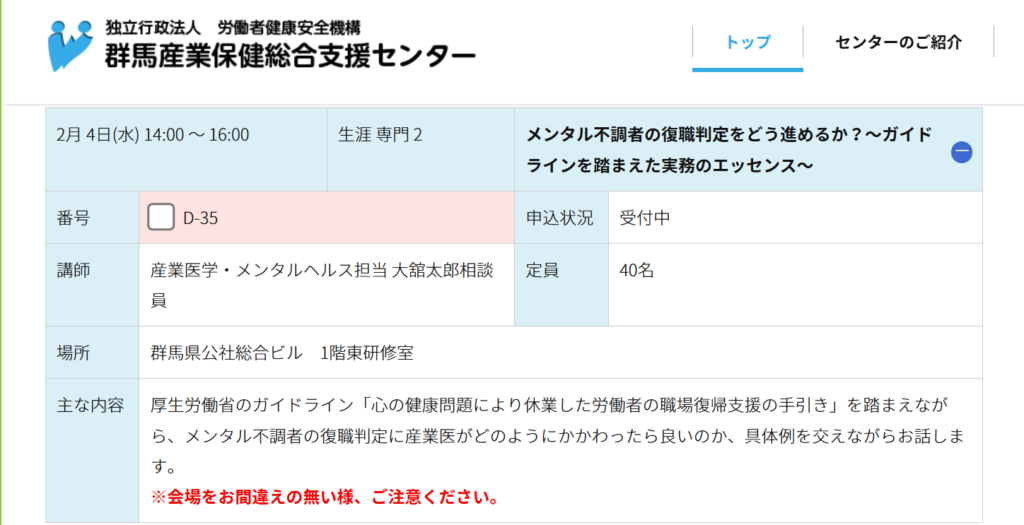契約に巡視・面談が明記されていない場合は違反になる可能性があります
産業医契約において、「職場巡視」や「面談(面接指導)」が契約書に明記されていない場合でも、実際に産業医がそれらの業務を行っていれば即座に法令違反とはなりません。ただし、契約内容と実際の業務が著しく乖離していたり、産業医が義務とされる業務を実施していない場合には、労働安全衛生法違反と見なされるリスクがあります。
産業医の法定業務と契約内容の関係
労働安全衛生法第13条および関連する厚生労働省令により、事業場に選任された産業医は以下の業務を行うことが義務付けられています:
- 毎月1回以上の職場巡視(一定規模以上の事業場)
- 長時間労働者に対する面接指導
- 労働者の健康保持増進に関する意見の表明
これらの業務が産業医の法的義務である以上、契約書にもそれに対応する内容を記載するのが望ましく、記載がない場合は契約の不備とされる可能性があります。また、実務上も産業医がその業務を行いやすくするために、契約書には具体的な業務内容を盛り込むべきです。
よくある誤解:契約外だからやらなくていい?
「契約に書いてないから巡視や面談はやらなくていい」という考えは誤りです。産業医の職務は法令に基づくものであり、契約書の有無や内容にかかわらず、選任された産業医には業務遂行義務があります。
逆に言えば、契約に明記していないことで業務が曖昧になり、産業医が法定業務を適切に行えなかった場合、事業者が法令違反を問われる可能性があります。また、産業医自身も職責を果たしていないと評価されるリスクがあります。
実務での注意点
実務では以下のような点に注意が必要です:
- 契約書に「職場巡視」「面接指導」などの項目が明記されているか確認
- 月1回の巡視が実施されておらず記録も残っていないケースは違反にあたる
- 長時間労働者への面談が産業医以外(例:保健師)で代行されているケースは、法的にはNG
- 契約書に明記していない業務を依頼される場合は、文書で補足しておくと安全
企業の人事担当者や産業医担当者が業務内容を十分に理解し、契約内容と実際の業務が一致しているかを定期的に確認することが重要です。
産業医の立場としての対応と推奨事項
産業医としては、契約締結前に業務範囲や頻度、報告方法などを明確にし、書面に反映させることが基本です。また、契約後も定期的に職場と業務内容についてすり合わせを行い、実態に即した契約内容にアップデートする姿勢が望まれます。
もし契約内容と実務に乖離がある場合は、速やかに見直しを提案し、適切な法的業務が遂行できる体制を整えることが、産業医としての責務といえます。
まとめ
契約内容に巡視や面談が含まれていないこと自体が即座に違反となるわけではありませんが、業務遂行の根拠として明記されていることが望ましく、記載がないことで誤解やトラブルにつながることもあります。産業医としては、契約と実務の整合性を重視し、法令遵守と労働者の健康保持の両立を図ることが重要です。